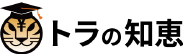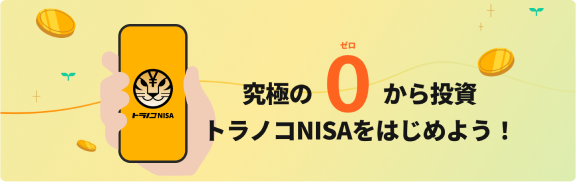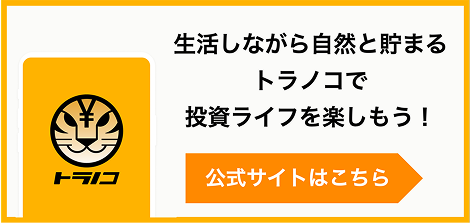夏のボーナスを賢く使う!貯蓄・保険・投資の選び方
公開日: 最終更新日:
夏のボーナス(賞与)は、1年間の収入の中でも大きなイベントの1つです。レジャーや趣味などに充てるのも良いですが、将来を見据えて賢く使うことも大切です。この記事では、夏のボーナスを「貯蓄」「保険」「投資」にどう振り分けるべきかをわかりやすく解説します。夏のボーナスの使い道を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
コンテンツ
夏のボーナスの平均額は?
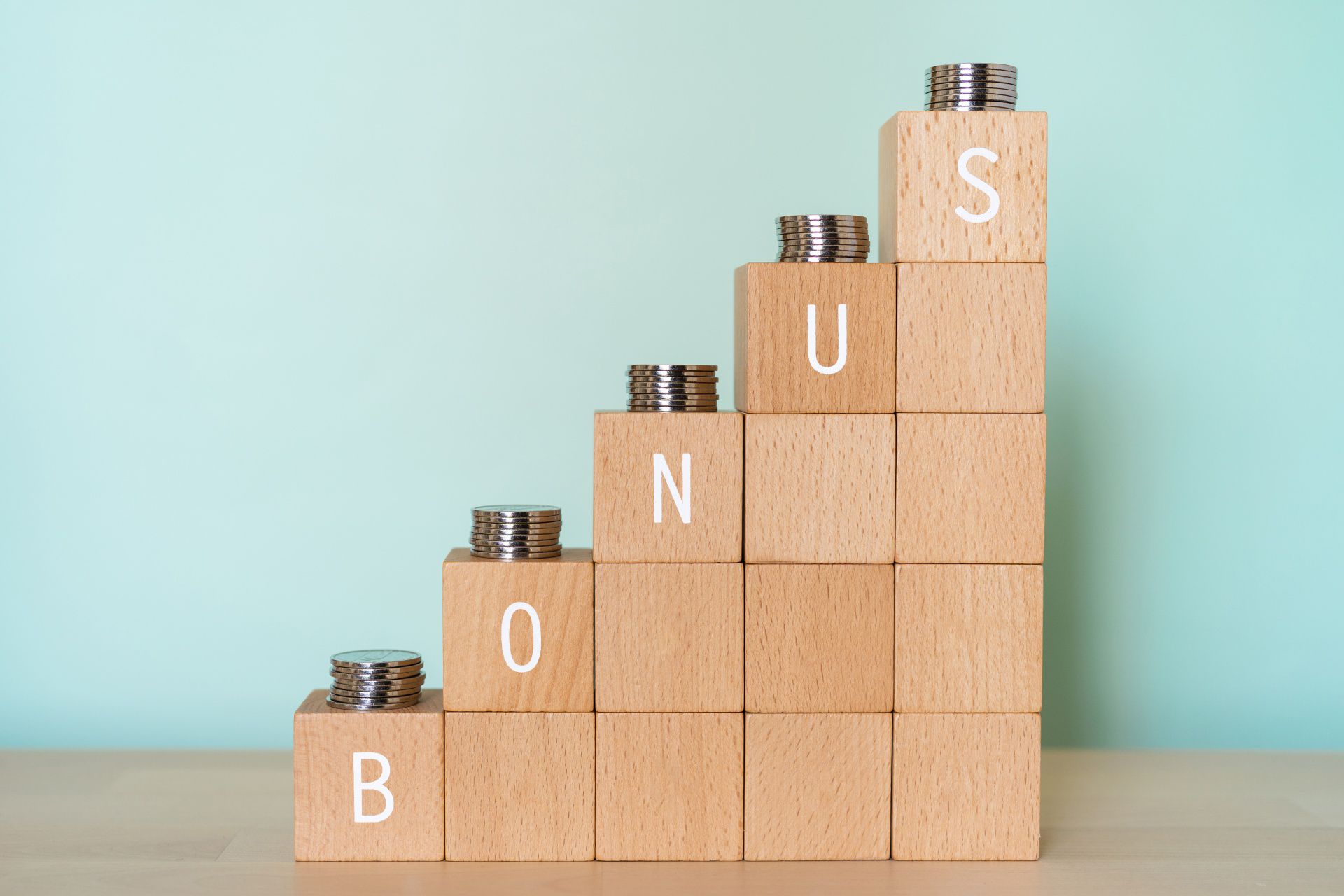
厚生労働省の調査によると、令和6年(2024年)の夏のボーナスの平均額は41万4,515円で、前年比2.3%増となりました。ただし、平均額はあくまでも目安です。年俸制が導入されている企業などでは、ボーナスの支給が無いケースもあります。実際の支給の有無や支給額は、業種や企業規模、勤続年数、役職などによって異なります。自身のボーナス額を把握したうえで、具体的な使い道を検討することが重要です。
出典:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年9月分結果速報等」
ボーナスの使い方を決める際のポイント

夏のボーナスを有効に活用するには、計画的に使う必要があります。具体的には、以下のポイントを意識するとよいでしょう。
使う・貯める・増やすのバランスを考える
ボーナスの使い方は、「使う」「貯める」「増やす」の3つに分けて考えるのがおすすめです。それぞれの具体的な使い道は以下の通りです。
| 使う | レジャー、趣味、欲しかったものを買う、自己投資 など |
| 貯める | 貯金、住宅ローン返済 など |
| 増やす(投資) | 投資信託、株式投資、NISA、iDeCo など |
ボーナスをすべて使う、またはすべて貯める(増やす)のではなく、使う・貯める・増やすの3つにバランスよく配分することを検討しましょう。例えば30%を使い、50%を貯金、20%を投資に回すといった具合です。
配分の割合に正解はありません。現在の貯蓄状況やライフプラン、レジャーの予定などに応じて自分にあった配分を検討しましょう。
関連記事:ライフプランのシミュレーション方法を解説。将来必要なお金を「見える化」しよう
目標を明確にして無駄遣いを防ぐ
ボーナスのようなまとまったお金が入ると気が大きくなり、無駄遣いをしてしまいがちです。しかし、何となく使ってしまうと後悔につながることもあります。家電の購入や将来のライフイベントなど、具体的な目標を立てて使い道を決めることが重要です。
夏のボーナスは、旅行やキャンプなどのレジャー費用に充てたい人も多いでしょう。以下の記事で、レジャー費用の平均額や節約するポイントを紹介しています。ぜひ参考にしてください。
関連記事:レジャー費用はどれくらい?平均額と計画的に貯蓄する方法を紹介
貯蓄:まずは急な出費や近い将来への備えを

夏のボーナスの使い道として、まず検討したいのが貯蓄です。ボーナスの一定割合を貯蓄に回すことで、想定外の事態に備えることができます。
ボーナスを貯蓄すべき理由
急なケガや病気、退職、冠婚葬祭、家電の故障など、日常生活において思いがけない出費が発生する可能性があります。また、旅行や車の買い替えなど、近い将来の支出にも備えておきたいところです。
ボーナスを貯蓄することによって、突発的な出費や将来のまとまった支出にも柔軟に対応しやすくなります。
貯蓄の目安
金融庁の資料によると、生活防衛資金として生活費の6ヵ月~1年分のお金を貯めておくことが理想とされています。仮に毎月の生活費が25万円であれば、150~300万円が目安です。一般的に短期間ですぐに用意できる金額ではないため、ボーナスを活用して準備していくとよいでしょう。
また、将来必要な支出(住宅購入の頭金、教育費など)がある場合は、具体的な金額を見積もって貯蓄に取り組む必要があります。
おすすめの貯蓄方法は?
財形貯蓄や積立定期預金で毎月の給与から積み立てをしている場合、ボーナス月だけ積立額を増額することが可能です。あらかじめ金額を設定しておけば、ボーナスのうち一定額が貯蓄に回るため手間がかかりません。
また、定期預金にするのも有効です。預入期間中は原則引き出すことができない代わりに、普通預金よりも高い金利が期待できます。なお、中途解約しても元本割れはしませんが、ペナルティとして適用利率が下がってしまうことがあるので注意しましょう。
関連記事:定期預金の中途解約はペナルティがある?デメリットと損しないための対策を紹介
保険:万が一のリスクに備える

夏のボーナスの使い道として、貯蓄の次に考えたいのが保険です。ここでは、保険の必要性や検討する際のポイントを紹介します。
保険の基本と必要性
保険は自分や家族が死亡したり、大きな病気になったりした際の経済的な負担を軽減してくれる仕組みです。保険料を払うことで、万が一のときには保険金が支払われます。特に子育て中の世帯は、保険に加入して十分な保障を確保する必要性は高いといえます。
おすすめの保険の種類
代表的なものとして、生命保険(死亡保険)、医療保険、がん保険などがあります。
| 生命保険 (死亡保険) |
被保険者(保険をかけられている人)が死亡または高度障害状態と なったときに保険金が支払われる |
| 医療保険 | 病気やケガの医療費に備えるための保険で、入院日数や手術などに応じて 保険金が支払われる |
| がん保険 | がん治療に特化した保障を確保できる保険で、がんと診断されたときや 所定のがん治療を受けたときに保険金が支払われる |
それぞれ役割が異なるため、自分や家族の経済状況やライフステージにあった保険を選ぶことが大切です。
関連記事:保険にはどんな種類がある?特徴や必要性をわかりやすく解説
ボーナスで保険を検討する際のポイント
「自分に万が一のことがあったときに家族が経済的に困らないようにしたい」「病気やケガの医療費に備えたい」など、目的によって最適な保険は異なります。そのため、まずは保険加入の目的を明確にすることが大切です。
また、複数の保険料品を比較したり、保険料と保障内容のバランスを検討したりする必要もあります。自分で選ぶのが難しいと感じたら、専門家に相談するのも1つの方法です。
『トラノコ保険相談』なら経験豊富なFPに無料で相談できる
『トラノコ保険相談』(提供:TORANOTEC株式会社)なら、経験豊富なファイナンシャルプランナー(FP)からライフスタイルや将来の目標に合わせた最適なプランを提案してもらえます。無料で相談することができ、無理な勧誘は一切ありません。
投資:ボーナスを運用して賢く増やす

ボーナスを投資に回し、将来に向けて資産を増やすのも有効な使い道です。ここでは、ボーナスを運用するメリットやリスク、おすすめの投資方法を紹介します。
ボーナスを投資に回すメリット
日本は低金利が長く続いており、預貯金だけでお金を増やすのは難しい状況にあります。ボーナスの一部を投資に回すことによって、預貯金だけでは得られないリターンが期待できることがあります。
また、投資はインフレ(継続的な物価上昇)への対策としても有効です。インフレが続くと、預貯金の実質的価値は目減りします。同じ商品・サービスを購入するのに、これまでよりも多くのお金が必要になるからです。株式などはインフレに強い資産といわれており、保有資産の一部に組み入れることで資産の目減りを防ぐ効果が期待できます。
投資のリスク・注意点
投資には元本割れリスクがあるため、しばらく使う予定がない余剰資金で行うことが大切です。また、投資先を複数の資産・銘柄に分散し、長期的な視点で投資に取り組むことでリスクの軽減が期待できます。
例えば、国内外の株式、債券、不動産など、複数の資産に分散して投資を行うことで、1つの資産に集中して投資するよりも価格変動をある程度抑えることができます。加えて、定期的に一定額を購入する積立投資を長く続ければ、高値のときにだけ買ってしまう心配がなく、購入単価が平準化されます。
初心者におすすめの投資方法は?
ボーナスで投資を始めるなら、投資信託がおすすめです。投資信託は、複数の投資家から集めた資金を1つにまとめ、専門家が株式や債券などで運用を行う金融商品です。少額から投資可能で、運用をプロに任せられるため、初心者の方でも続けやすいでしょう。
投資アプリ『トラノコ』なら3つのファンドから選ぶだけ
投資信託は商品数が多いため、自分にあったファンドを選ぶのは難しいかもしれません。投資アプリ『トラノコ』なら、以下3つのファンドから選ぶだけで本格的な分散投資を行うことができます。
- 大トラ(リターン重視)
- 中トラ(バランス重視)
- 小トラ(安定重視)
いずれも世界の株式、債券、不動産、商品などに幅広く分散投資を行うため、リスクを抑えながら将来に向けて資産を作ることが可能です。
まとめ
夏のボーナスは、計画的に使うことで家計の安定や資産形成につながります。使う・貯める・増やすのバランスを意識して、自分にあった使い方を決めることが大切です。「貯蓄」「保険」「投資」の必要性を理解し、ボーナスをどう振り分けるべきか検討しましょう。