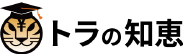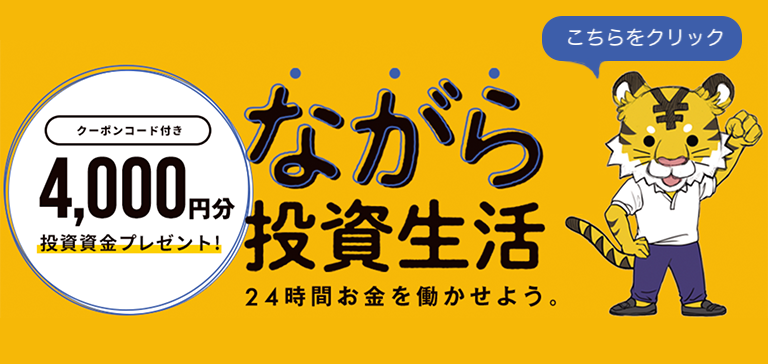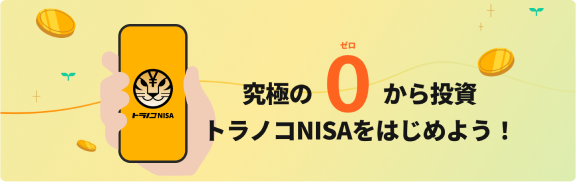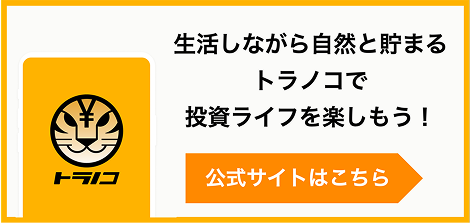資産形成は早いうちから始めよう!新社会人の資産形成の始め方とおすすめの方法を紹介
公開日: 最終更新日:
新社会人になり、投資や貯蓄といった資産形成に興味を持ち始める方もいるでしょう。資産形成を成功させるためには、基礎的な知識を身につけたうえで早めに実践することが大切です。本記事では、資産形成の上手な始め方と、新社会人が始めやすい資産形成の方法を紹介します。資産形成を始めたいけど、何から手を付けてよいかわからない新社会人の方は必見です。
コンテンツ
資産形成は早く始めるほど効果がある
資産形成とは、将来のために必要な資産を築くことです。人生には、次のように節目となる出来事「ライフイベント」があり、これらのタイミングにはまとまったお金が必要になります。
● ライフイベントの例
・ 留学・資格取得
・車の購入
・マイホーム購入
・結婚・出産
・子どもの教育
・自宅のリフォーム
・定年(老後生活)
・介護
ライフイベントで必要になるお金は毎月の給料だけでは賄えないことも多いため、将来を見据えて計画的に資産形成しておくことが大切です。
時間を味方につける「複利効果」
資産形成は早くから始めることで「複利効果」が得やすくなるため、効率よく資産を増やせます。複利効果とは、投資で得た利益を再び投資にまわすことで、利益が利益を生み、「雪だるま式」に資産が膨らんでいく効果です。
例えば、毎月1万円ずつ積み立てて年利3%と運用した場合、3年後の資産は約38万円(元本36万円、運用収益2万円)ですが、30年後の資産は約583万円(元本360万円、運用収益223万円)です。長く積み立てることで、元本に対する運用収益が大きく増えていることがわかります。
複利効果についてはこちらの記事で詳しく解説しているのでチェックしてみてください。
関連記事:複利運用は利益が利益を生む運用方法。具体的な方法をチェック
新社会人必見!資産形成の始め方

どのように資産形成を始めたらよいかわからない方は、次のステップを参考に実践してみましょう。
【ステップ1】毎月いくら資産形成にまわせるかを見極める
資産形成への第一歩目は、毎月どのくらいの金額を資産形成にまわせるか見極めることです。新社会人になったばかりで家計管理に不慣れな方は、まずはここから始める必要があります。
資産形成にまわせるお金は、手取り収入から生活費を差し引いた金額です。例えば、手取り月収が17万円、1か月あたりの生活費が15万円であれば、資産形成にまわせるお金は月2万円です。1か月あたりの生活費がわからない方は、家計簿をつけるなどして金額を把握しましょう。
家計簿と聞くと面倒くさいイメージをお持ちの方もいるかもしれません。そのような方は家計簿アプリを活用しましょう。銀行口座やクレジットカード、電子マネーなどのデータを連携できるサービスもあるので、手間なく支出を管理したい方におすすめです。
【ステップ2】目標額を決める
資産形成にまわせる金額がわかったら、目標額を決めます。この際、「マイホーム購入のために〇〇万円」というように具体的な目的も合わせて決めておくとよいでしょう。就職したばかりで将来のライフイベントがイメージできない方は、「将来のために〇〇万円」などでも構いません。目標額を決めることで、資産形成を継続するモチベーションをキープしやすくなります。
資産形成の目標額を決める際は、公的機関や金融機関が提供しているシミュレーターを活用すると便利です。例えば、金融庁が提供している「つみたてシミュレーター」では必要項目を入力することで、将来貯められる金額や、目標金額を達成するために必要な積立金額を自動計算できます。
【参考】金融庁「つみたてシミュレーター」
【ステップ3】資産形成方法を選ぶ
資産形成の目標額が決まったら、資産形成の方法を選びましょう。資産形成の方法は大きく分けると「貯蓄」と「投資」に分類できます。
貯蓄とは、金融機関などにお金を預けて「蓄える」ことです。主に銀行の預貯金(普通預金や定期預金)に預けることを言います。貯蓄は元本が保証されるため、すぐに使うお金や、使い道が決まっているお金を確実に準備するのに適しています。ただし現在は預貯金の金利が低いため、大きく資産を増やすのが難しい状況です。
投資は、将来有望な投資先にお金を投じることです。代表的な投資商品には、株式や投資信託、債券などがあります。投資は投資先の成長に応じたリターンが得られるため、資産を大きく増やせる可能性があります。その一方で、投資先の業績や経済状況によっては資産が目減りする場合もあります。
投資は元本保証がないため、「余裕資金」で始めることが基本です。余裕資金とは、当面使う予定のないお金のことです。余裕資金で投資をすれば、長い時間をかけて運用できるため、複利効果で資産を増やしやすくなりますし、仮に元本割れしてもリカバリーする時間が確保できます。
また、投資にはハイリスク・ハイリターンの原則があることも知っておきましょう。これは「リターンの大きい商品ほどリスクも大きく、リターンの少ない商品ほどリターンは少ない」という投資の特徴を意味します。投資商品によってリスク・リターンの大きさは異なるので、ご自身のリスク許容度に合った商品を選びましょう。
このように貯蓄と投資はそれぞれ特徴が違うため、自分の目的に合った方法で始めるのが大前提です。ただし、貯蓄だけでは効率よく資産を増やせないので、少額からでも早めに投資にもチャレンジして慣れておくのがよいでしょう。
投資についてはこちらの動画でわかりやすく解説しているので、参考にしてみてください。
関連動画:05-投資の三大原則
新社会人が始めやすい資産形成3選

ここでは新社会人の方が始めやすい代表的な資産形成の方法を紹介します。運用期間や目的に応じた方法を選びましょう。
【運用期間:短~中期】預金の自動積立や財形貯蓄
緊急予備資金や使い道が決まっているお金は、元本が保証される預金で準備するのが適しています。このようなお金を投資で準備すると、お金が必要なタイミングで値下がりしている可能性もあるため、預金で確実に目標額を貯めるのがよいでしょう。
緊急予備資金とは、災害や病気など不測の事態に備えるためのお金です。緊急予備資金は生活費の最低でも3か月分程度を目標に貯めておきましょう。被災した場合の生活を立て直す資金や、働けなくなったときの生活としてすぐに引き出せるよう、普通預金で準備することをおすすめします。
すでに使い道が決まっているお金は、預け入れ期間が決まっている定期預金で準備するのが適しています。基本的に満期日までは引き出せませんが、普通預金より高い金利で運用できます。例えば、3年後に住宅購入資金が必要なら3年定期、というようにお金が必要になる時期に合った期間の定期預金を契約しましょう。
自動積立定期や目的別口座(預金口座内に目的別の口座が作れるサービス)を利用すれば、毎月決まった金額を自動的に貯められるので、ついつい貯めるべきお金を使ってしまう心配がありません。
勤務先に財形貯蓄がある場合は、これを活用するのも一案です。財形貯蓄とは、毎月の給与や賞与から天引きして自動的に貯蓄できる制度です。財形貯蓄には「一般財形」「住宅財形」「年金財形」の3種類があります。一般財形は使い道が自由で、預け入れ開始から1年経過すれば全額または一部を引き出すことも可能です。住宅財形は住宅の取得・増改築などの目的、年金財形は老後の資金づくりを目的とした制度です。それぞれ最低積立期間や払い出し時のルールなどが異なるので、目的に合った種類を選びましょう。
参考:厚生労働省「財形貯蓄制度」
【運用期間:中~長期】NISA(少額投資非課税制度)
投資を始めるなら、少額からの長期・分散投資に適したNISAが便利です。NISAとは投資で得た利益が非課税になる制度です。NISAの資金の使い道は自由で、いつでも引き出せるため、柔軟に中長期的な資産形成を行えます。
NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つがあります。両者は併用できますが、投資初心者ならつみたて投資枠が利用しやすいでしょう。つみたて投資枠で投資できる商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限定されているので、投資するタイミングを見極める必要がなく、ハイリスクの商品に手を出してしまう心配もありません。
NISAについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:2024年から新NISAがスタート!旧NISAとの違いをわかりやすく解説
【運用期間:長期】iDeCo(個人型確定拠出年金)
老後資金を貯めるなら、iDeCoでの運用もおすすめです。iDeCoとは、公的年金(国民年金・厚生年金)に上乗せして自分自身で年金を積み立てて運用できる制度です。
iDeCoの主なメリットは節税効果が高いことです。その年に積み立てた掛金の全額が所得控除(所得税・住民税の基礎となる所得金額から差し引ける仕組み)の対象となるため、間接的に税負担を抑える効果があります。また、運用益に税金がかからず、受取時にも税制優遇が受けられるため、老後資金を準備しながら税負担を抑えたい方に適しています。
ただしiDeCoの運用資金は原則60歳まで引き出せないため、20代の新社会人の方がiDeCoを始める場合、最低でも30年以上、出金ができないことを前提としておく必要があります。
iDeCoの最低掛金額は月5,000円ですが、その金額を投資にまわすお金に余裕がない方や、60歳になる前にまとまったお金を使いたい可能性がある場合は、預金やNISAなど他の方法で資産形成を始めるのが良いでしょう。
関連記事:iDeCoの節税効果はどのくらいお得?3つの税制メリットとシミュレーションを紹介
手軽に投資を始めるなら「トラノコ」がおすすめ
早いうちから投資にチャレンジしたい方は、投資アプリ「トラノコ」の利用を検討してみましょう。証券会社でNISA口座を開設した場合、多くの金融商品の中から投資先を選ぶ必要がありますが、トラノコなら3つの投資信託の中から、リスク許容度に応じた商品を選ぶだけ。どの商品を選んだらよいか分からない方でも安心です。またNISAにも対応しているので、投資の利益が税金で目減りしません。
毎月の積立金額もフレキシブルに変更できるので、少額から手軽に始めたい方にも適しています。お買い物のおつりやポイント・マイルを自動的に積み立てられる機能もあるので、楽しみながら投資したい方にもおすすめです。
まとめ
資産形成は早めに始めることで、効率よく資産を増やしやすくなります。資産形成の目的によって適した方法は異なるので、ご自身に合った方法を選んで実践しましょう。ただし、老後資金など具体的な使い道が決まっていないお金を準備する場合は、貯蓄より投資のほうが効率よく準備できます。少額からでも早めに投資にチャレンジして、資産形成を成功させましょう。