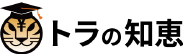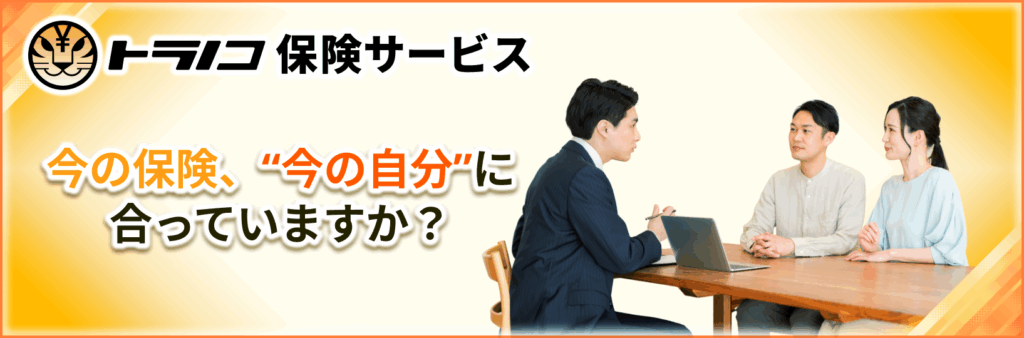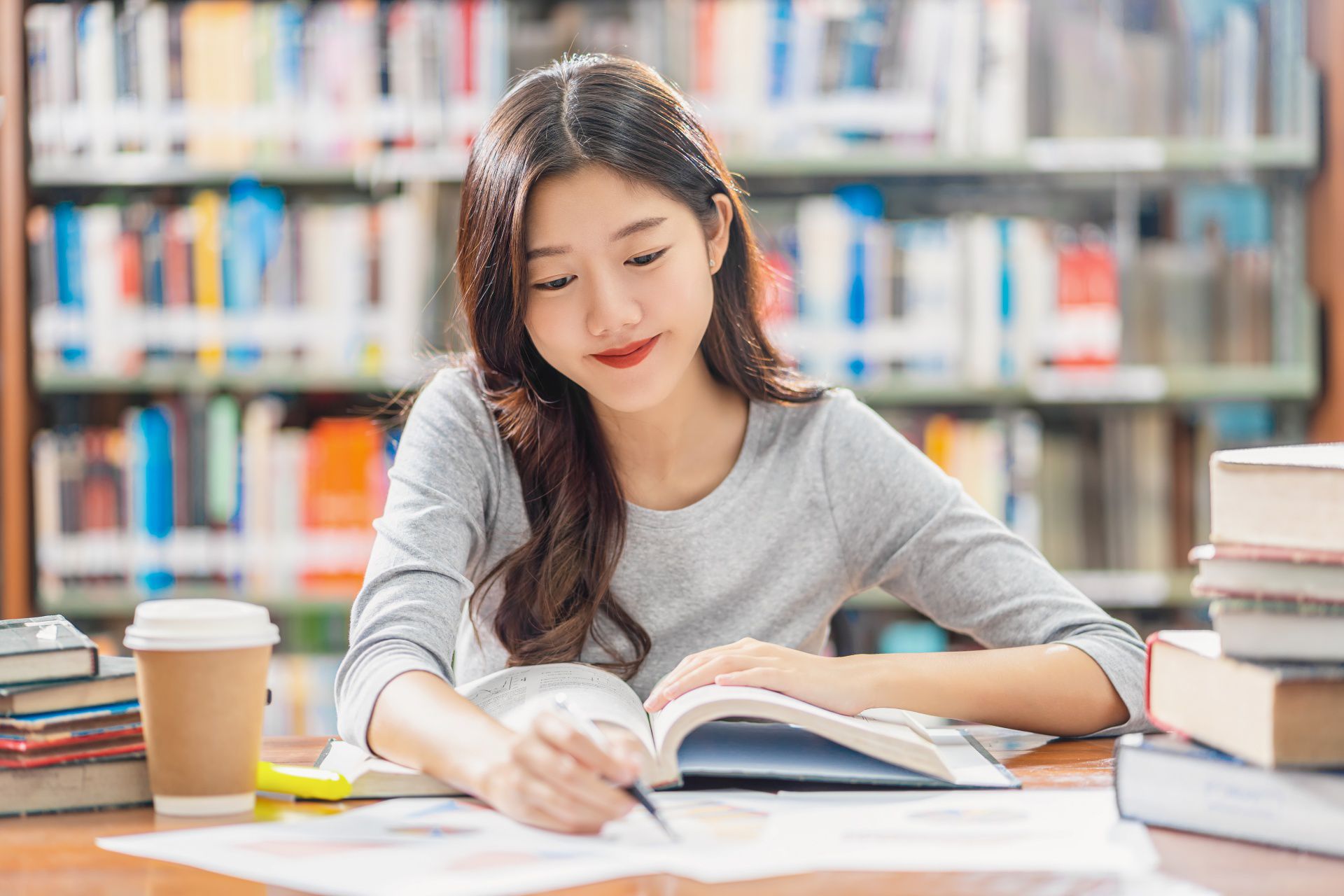金利が上がると生活はどうなる?家計への影響と必要な備えをわかりやすく解説
公開日:
近年、日本でも金利が上昇傾向にあります。金利が上がると私たちの生活にどんな影響があり、どのような備えが必要になるのでしょうか。この記事では、金利が上がる理由や家計への影響、具体的な対策について解説します。
そもそも金利とは何か

金利とは、お金の貸し借りにおいて発生する利息の割合です。通常はパーセント(%)で表記します。利息は、お金を借りた人が貸した人へ支払う対価(利用料)のことで、借りた金額に応じて発生します。
お金を預けると利息がもらえる
銀行にお金を預けると、半年などの一定期間ごとに利息がもらえます。銀行は預かったお金を企業などに貸し出して利益を得ており、その一部が預金者に還元される仕組みになっています。
例えば、金利1%の定期預金に100万円を預け入れると、1年間に1万円(100万円×1%)の利息がつきます(税金は考慮外)。
関連記事)定期預金の中途解約はペナルティがある?デメリットと損しないための対策を紹介
https://toranochie.com/column/fixed-term-deposit_penalty/
お金を借りると利息を支払う必要がある
一方で、住宅ローンや車のローンなどを利用してお金を借りると、元本に利息を上乗せして返済しなくてはなりません。金利が高くなるほど、借りる側の返済負担は大きくなります。
例えば、100万円を借りて金利3%で1年後に返済する場合、元金100万円と利息3万円(100万円×3%)の合計103万円を支払う必要があります。
金利と日銀の金融政策との関係

金利は、日本銀行(日銀)の金融政策に大きく左右されます。金融政策とは、中央銀行(日本では日銀)が物価を安定させるために行う政策のことです。日銀は、景気・物価の現状や見通しを分析したうえで政策金利の水準を調整しています。
政策金利とは、景気や物価の安定のために中央銀行が設定する短期金利です。金融機関の預金金利や各種ローン金利などに影響を与えます。
好景気のときは金利を引き上げる
一般的に、日銀は好景気のときには政策金利を引き上げます。景気がよくなりすぎると、継続的に物価が上昇するインフレが発生して経済に影響が出るからです。
政策金利が上がると、金融機関は貸出金利を引き上げます。企業や個人はお金を借りにくくなり、企業の投資活動や個人消費が縮小するため、景気の過熱や物価上昇を落ち着かせる効果が期待できます。
不景気のときは金利を引き下げる
反対に、日銀は不景気のときには政策金利を引き下げます。
不景気になると、継続的に物価が下落するデフレが発生します。不況で商品やサービスが売れず、企業の利益が減って従業員の給与が下がり、人々の消費が低迷してさらに景気が悪くなるという悪循環が起こりやすくなります。
政策金利が下がると、金融機関は貸出金利を引き下げます。企業や個人はお金を借りやすくなるため、企業の投資活動や個人消費が活発になり、景気回復につながります。また、物価も上がりやすくなります。
関連記事)「インフレ」「デフレ」ってなに?物価との関係やインフレ時に始めやすい資産運用をわかりやすく解説
https://toranochie.com/column/what-is_inflation_deflation/
日本で金利が上がっている理由

日本は物価が上がらないデフレが長年続いていたことから、日銀は低金利政策をとっていました。しかし、2024年以降は物価が上昇し、企業の賃上げの動きも広がりつつあります。
こうした動きを受けて、日銀は2024年3月にマイナス金利を解除しました。さらに同年7月には政策金利を0.25%へ引き上げ、2025年1月には0.5%へ引き上げる追加利上げも実施しました。
ただし、米国のトランプ政権による関税政策などの影響で、世界的な景気の減速リスクなどの不透明な要素もあります。そのため、今後も金利が上がり続けるかどうかは状況次第といえるでしょう。
金利が上がると家計にどんな影響がある?

金利の上昇は、家計にとってメリットとデメリットがあります。具体的には、次のような影響が出る可能性があります。
預貯金や債券の金利が上がる
金利が上がると連動して預貯金の金利も上がるため、より多くの利息を受け取ることができます。また、個人向け国債などの債券の利回りも上昇する傾向にあります。
安全性を重視し、普通預金や定期預金、個人向け国債などの元本保証商品で運用したい人にとっては大きなメリットといえます。
保険の予定利率が上がる
金利が上がると保険会社は予定利率を引き上げるため、保険料が下がる可能性があります。
予定利率とは、生命保険会社などが契約者に対して約束する運用利回りです。保険会社は、契約者から受け取った保険料を株式や債券などで運用し、その運用収益を契約者に支払う保険金や解約返戻金に充てています。
保険会社は、予定利率をもとに運用収益を見込んで保険料を決定します。予定利率が上がるとより多くの運用収益が見込めるため、保険料が下がる傾向にあります。
ただし、予定利率の引き上げによって保険料が下がるのは、新たに契約する保険商品に限られます。契約期間中に保険会社が予定利率を引き上げても、保険料の金額は変わらないため注意しましょう。
物価上昇を抑える効果が期待できる
先述の通り、日銀は過度なインフレを抑制する目的で利上げを実施することがあります。物価上昇が続くと、食料品や日用品などの生活必需品の価格も上がってしまいます。利上げは物価を押し下げる効果があるため、長期的には家計の負担軽減につながる可能性があります。
住宅ローン金利が上がる
日銀が政策金利を引き上げると、変動型の住宅ローン金利が上がり、毎月の返済額や総返済額が増える可能性があります。
住宅ローンの変動金利は、金融機関が1年未満の短期貸し出しに適用する最優遇金利である「短期プライムレート」をもとに決まることが多いです。短期プライムレートは政策金利に連動するため、日銀の利上げにより住宅ローンの変動金利も上がるかもしれません。
給与などの毎月の収入は変わらない一方で、住宅ローンの返済負担が増える可能性があるため注意が必要です。
円高が進みやすくなる
お金は、金利が高い通貨で運用するほうがより多くの収益が期待できます。日本で金利が上がると円が買われやすくなるため、結果として円高が進みやすくなります。
円高になると、輸入品を安く買えるのがメリットです。また、外貨の調達コストが下がり、海外旅行に行きやすくなります。ただし、海外の株式や債券などの外貨建て資産を持っている場合は、円換算後の価値が目減りしてしまうデメリットもあります。

金利が上がるときに必要な備えとは

金利が上がる局面では、家計の支出増加に対する備えが必要です。ここでは、具体的な対策を3つ紹介します。
家計を見直して無駄な支出を抑える
まずは家計を見直して、無駄な支出を減らすことに取り組みましょう。
生活費には、毎月または定期的に決まった金額を支払う固定費と、月によって支払う金額が変わる変動費があります。まずは固定費から見直すのがおすすめです。固定費は毎月の支払い額が決まっているため、一度見直せばその節約効果が長く続きます。
食費や娯楽費などは減らしすぎるとストレスが溜まり、節約が長続きしないことがあります。
関連記事)新社会人が身につけるべき家計管理の方法は?無理なく貯蓄するコツも紹介
https://toranochie.com/column/new-workingadult-managehouseholdfinances/
住宅ローンの借り換え・繰り上げ返済を検討する
現在の住宅ローンの返済条件を確認したうえで、必要に応じて借り換えや繰り上げ返済を検討しましょう。
完済までの期間が長く、今後も金利が上がると考えられる場合は、固定金利型の住宅ローンへ借り換えるのも選択肢です。ただし、借り換えには手数料がかかるため、コストに見合うだけのメリットがあるかを慎重に見極める必要があるでしょう。
手元にまとまった資金がある場合は、繰り上げ返済を行う方法もあります。元金の一部を前倒しで返済することで、利息の負担が軽減されるため、総返済額を減らすことができます。
保険の見直しを行う
金利が上がる局面は、保険の見直しを行う絶好のタイミングです。金利が上がって予定利率が引き上げられると、同じ保険金額でもこれまでより保険料が下がる可能性があります。
「昔入った保険がそのままになっている」「毎月の保険料が高いと感じる」という場合や、ライフステージが変わっている場合などは、今の保険が自分に合っているかを再確認してみましょう。
『トラノコ保険相談』ならFPに無料で相談できる
「保険を見直したい」と思っても、自分で保障内容が適切かを判断したり、複数の保険商品を比較したりするのは難しいかもしれません。
『トラノコ保険相談』なら、経験豊富なファイナンシャルプランナー(FP)に最適なプランを無料で提案してもらえます。オンラインでも対面でも相談でき、無理な勧誘は一切ありません。
まとめ
金利が上がると、家計にさまざまな影響が出る可能性があります。預貯金や保険などはプラスの面もありますが、住宅ローン金利の上昇などで家計への負担が増えるかもしれません。日々の支出や住宅ローン契約、加入中の保険の見直しなどに取り組み、家計の支出増加に備えましょう。