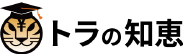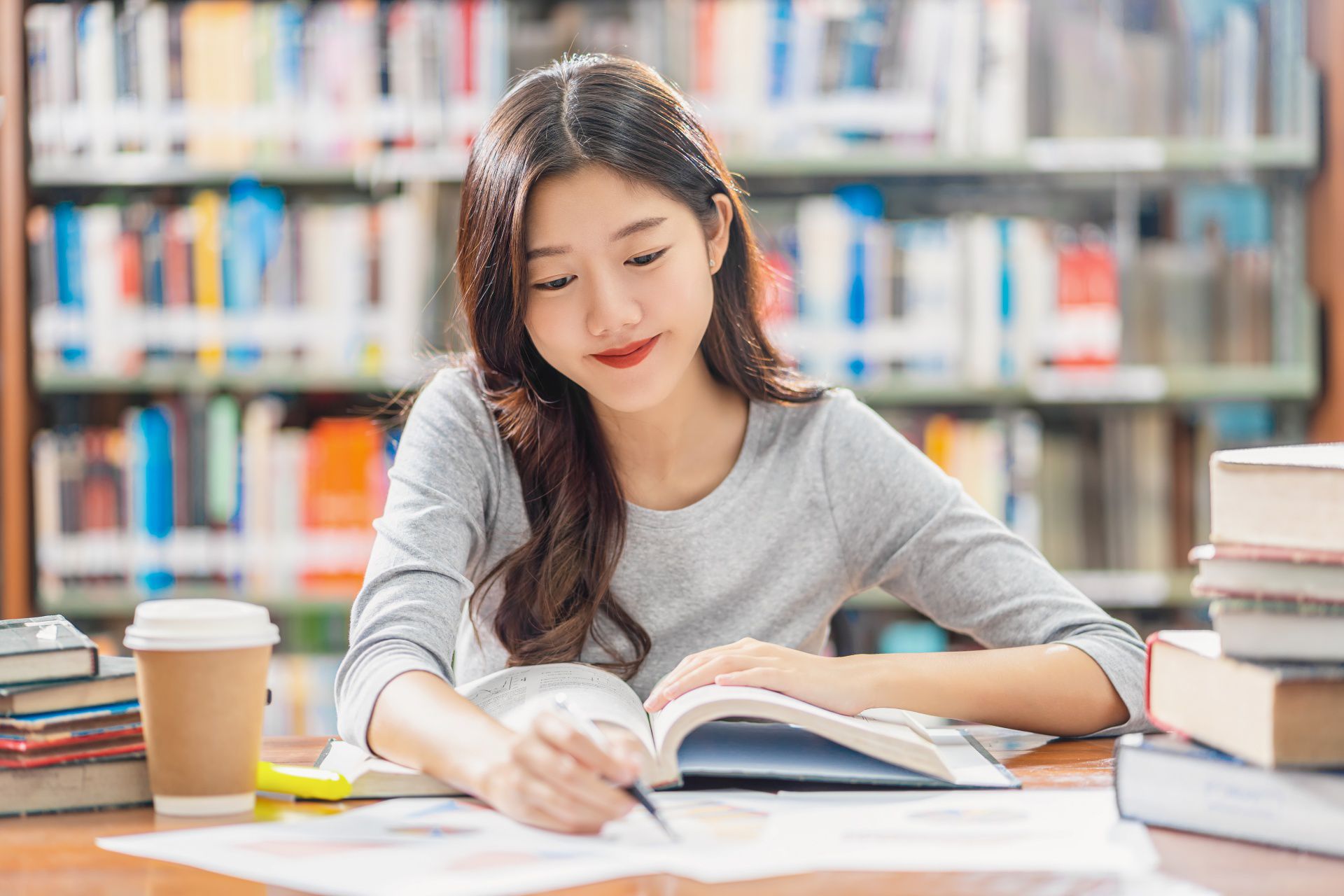関税とは?誰がいつ払う?課税の仕組みや種類、日本経済への影響をわかりやすく解説
公開日:
関税は、輸入品にかかる税金です。ニュースで耳にする機会は多いものの、「誰がいつ払うのか」「なぜ関税が課されるのか」といった疑問を持つ人は多いのではないでしょうか。この記事では、関税の仕組みや種類、日本経済への影響までわかりやすく解説します。
コンテンツ
関税とは

関税とは、海外からの輸入品に国が課す税金です。消費者は普段意識することが少ない存在ですが、実際は私たちの生活に大きく関わっています。まずは関税の基本的な仕組み、相互関税・追加関税との違いについて見ていきましょう。
関税は誰がいつ払う?
関税を払うのは、商品の輸入者です。例えば、日本が海外から商品を輸入する場合、日本の空港や港に輸入品が到着した際に、輸入者である日本の企業や個人が支払います。
仮に関税率5%の商品を1,000万円分輸入するとします。その場合、輸入者が負担する関税は50万円(1,000万円×5%)です。消費者が直接払うことはありませんが、関税は最終的に商品の価格に反映されます。そのため、結果として消費者の購買価格に影響を与えます。
相互関税・追加関税との違い
通常の関税のほかに、相互関税・追加関税と呼ばれるものもあります。
相互関税とは、貿易相手国が高い関税を課している場合に、自国の関税を相手国と同じ水準まで引き上げる措置です。報復的な性格を持ち、国際的な交渉カードとなることがあります。
追加関税は、輸入が急増して国内産業に悪影響を与える場合などに、通常の関税に上乗せされるものです。特定の産業を守るために、一時的に導入されることがあります。
国が関税をかける目的

海外からの輸入品にはなぜ関税が課されるのでしょうか。ここでは、関税の主な目的を2つ紹介します。
国内産業を保護するため
関税は、国内産業を守る役割を担っています。
関税をかけると輸入品のコストが上昇し、販売価格に反映されます。一方、国内で作ったものを販売する企業は関税を払う必要がありません。関税を課すことで、国内における輸入品の競争力が低下するため、国内産業を保護することにつながります。
国の収入を増やすため
国の収入を増やすことも、関税の目的の一つです。輸入品に関税をかけると、輸入者は国に税金を払うことになります。輸入する国にとって、関税は国の税収を増やす財源としての役割があります。
ただし、経済が発展するにつれて、国内の課税体制は所得税や法人税、消費税が中心になっており、関税の占める割合は小さくなっています。日本の令和7年度予算案ベースでは、国税税収78兆4,400億円のうち、関税の割合は約1.3%(9,890億円)です。
途上国では現在も関税が重要財源となっている国もありますが、先進国では国内産業を保護する役割が大きいといえるでしょう。
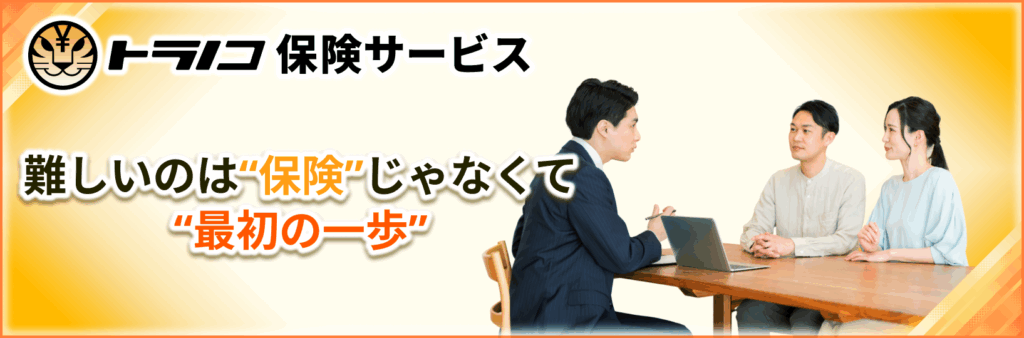
関税率の種類

関税率は、大きく「国定税率」と「条約に基づく税率」の2種類があります。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
国定税率
国定税率とは、法律に基づいて定められている関税率です。日本では以下の5種類があります。
| 国定税率の種類 | 内容 |
| 基本税率 | 国内産業保護を目的とした標準的な税率 |
| 暫定税率 | 政策上の必要に応じて基本税率を一時的に修正した税率 |
| 特恵税率 | 開発発展途上国からの輸入を対象とした低い税率 |
| 簡易税率(入国者携帯品) | 旅行者の携帯品や別送品に適用される総合的な税率 |
| 簡易税率(少額輸入品) | 課税価格20万円以下の少額輸入品に適用される税率 |
基本税率は国内外の価格差や必要な保護水準を考慮し、長期的な視点で設定されています。暫定税率は政策上の必要性などから、一定期間に限り基本税率に優先して適用されます。特恵税率は開発途上国・地域を支援する観点から、最恵国待遇の例外として適用されるものです。その他に、入国者の携帯品や20万円以下の少額輸入貨物に適用される簡易税率もあります。
条約に基づく税率
国定税率のほかに、条約に基づいて定められている関税率もあります。具体的には以下の2種類です。
| 条約に基づく税率の種類 | 内容 |
| 協定税率 | WTO加盟国・地域に適用される最恵国税率 |
| EPA税率 | 経済連携協定を結んだ国・地域に適用される特別税率 |
協定税率は、WTO(世界貿易機関)に加盟している国・地域に対して一定率以上の関税を課さないと約束されているものです。国定税率よりも低い場合に適用されます。
EPA(経済連携協定)とは、2国間または複数の国・地域間で貿易や投資を促進するために結ばれる協定です。経済連携協定の参加国間で、関税の引き下げや撤廃が行われます。EPA税率は経済連携協定を締結した国・地域からの輸入品を対象に、それぞれの協定に基づいて適用されるものです。
関税率の適用順位
原則として、関税率は「特恵税率、協定税率、暫定税率、基本税率」の順に優先して適用されます。ただし、特恵税率は「対象国の原産品であること」といった条件を満たす場合に限られます。また、協定税率は暫定税率や基本税率より低い場合に適用されます。
関税がかからないケースはある?
すべての輸入品に関税がかかるわけではありません。日本への輸入品の場合、例えば課税価格の合計額が1万円以下の物品は関税が免除されます。また、時計やパソコン、楽器、美術品、化粧品などは関税が無税となります。
ただし、これらはあくまでも目安です。原産国や品目の材質、加工の有無などによって関税率が変わる可能性もあります。正確な関税率を知りたい場合は、あらかじめ税関に照会を行うとよいでしょう。
海外からの輸入品にかかる関税は日本経済にどんな影響を与える?

関税には、国内産業を保護するなどの役割があります。その一方で、関税率が変動すると、消費者や企業活動に大きな影響を与えます。具体的にどんな影響があるのかを紹介します。
関税率引き上げによる影響
関税率が引き上げられると、輸入品の価格は上昇します。結果として、消費者は高い商品を購入せざるを得なくなり、家計の負担が増加します。日本は生活必需品の多くを輸入に頼っているため、関税率が上昇すれば景気にマイナスとなる可能性があるでしょう。
一方で、輸入品の価格が上昇すれば国内製品には有利に働くため、国内産業の保護につながることもあります。ただし、貿易相手国から報復関税を招くリスクがあり、国際関係全体に緊張をもたらす点にも注意が必要です。
関連記事:物価高対策で食費を節約するコツは?無理なく支出を抑える方法・考え方を紹介
関税率引き下げによる影響
関税率を引き下げると、輸入品の価格が下がります。食料などの生活必需品が安く購入できれば、家計に余裕が生まれるでしょう。輸入原材料を扱う企業にとってもコストが下がり、競争力強化につながります。
さらに、関税率の引き下げは貿易相手国との信頼関係を深め、自由貿易や経済連携協定を通じた協力強化につながるかもしれません。ただし、国内産業が輸入品に押されて打撃を受け、農業や製造業の存続に関わる可能性もあるのがデメリットといえます。
まとめ
関税は輸入品に課される税金であり、最終的には私たちの生活コストに影響を与えます。主な目的は「国内産業の保護」と「国の収入を増やす」の2つです。ただし、グローバル経済が複雑化するなか、近年では関税政策が国際的な交渉カードとして重要な役割を果たす場合もあります。
関税の仕組みを理解することは、ニュースの背景を読み解くだけでなく、現在や将来の生活を考えるうえでも重要なことです。関税をめぐる政策やニュースを自分ごととして捉え、将来の生活設計に役立てていきましょう。