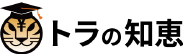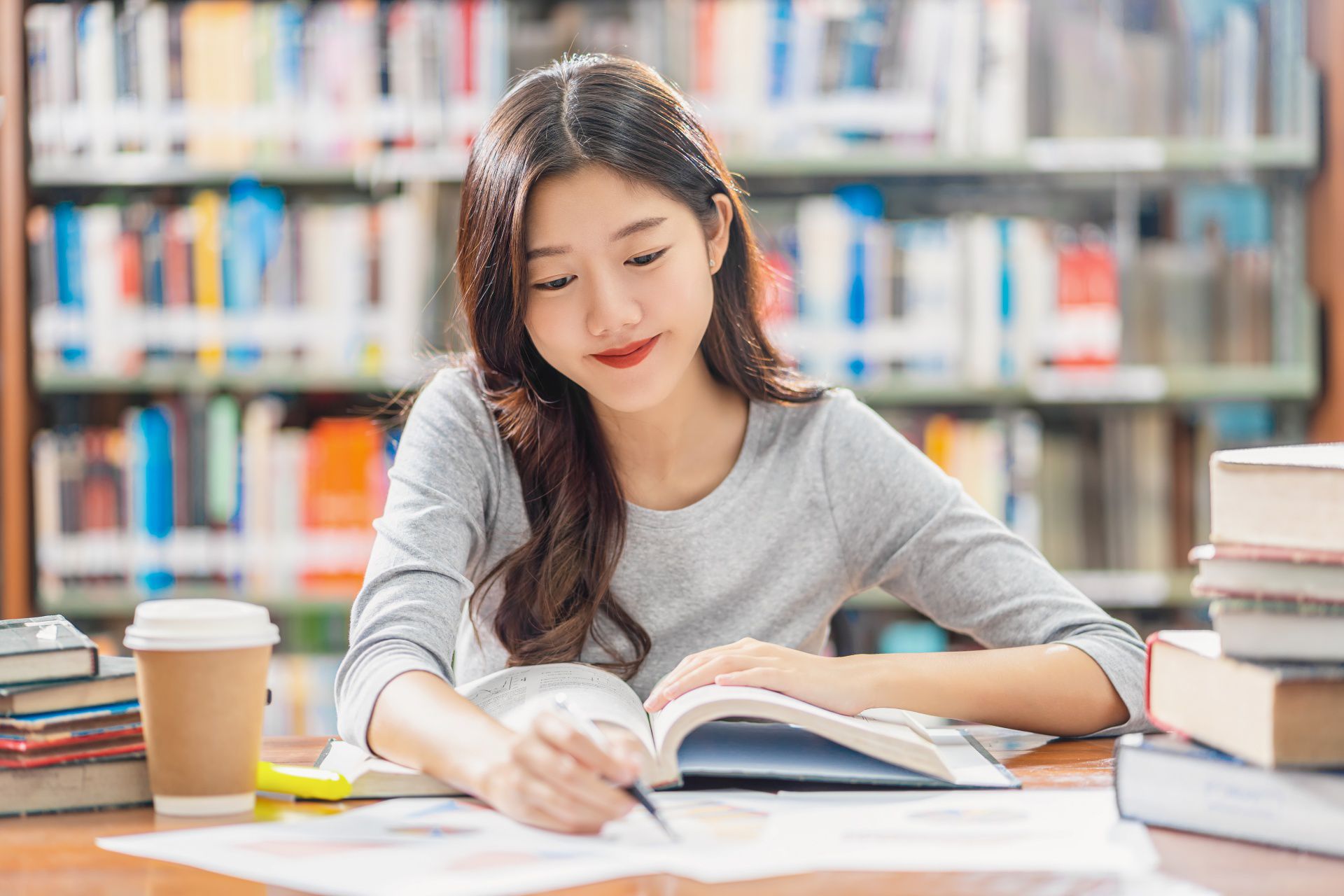学びの秋に始めよう!「お金の勉強」入門ガイド
公開日:
秋といえば、何か新しいことを始めたくなる季節です。自己投資のひとつとして“一生使えるスキル”である「お金の勉強」にチャレンジしてみませんか?社会人として知っておきたいお金の基本知識や、おすすめの勉強方法など、初心者でも手軽に始められる内容をご紹介します。
コンテンツ
なぜ「今」、お金の勉強なのか?

秋は「学びの季節」と言われます。夏の暑さが落ち着き、心も身体も落ち着いて物事に取り組みやすいこの時期は、読書や勉強を始めるには絶好のタイミングです。自己成長やスキルアップに目を向ける方も多いこの季節、気軽に「お金の勉強」にも取り組んでみてはいかがでしょうか。
2022年4月からは、高校の家庭科において金融教育が必修化されました。若いうちから「お金について学ぶ」ことが、もはや特別なことではなく、社会の常識として求められる時代に入ってきました。これからは、誰もが金融知識を身につけるべきという認識がますます広がっていくでしょう。
特に社会人にとって、お金の知識は「生きる力」と直結しています。給与や税金、保険、住宅ローン、老後の年金、資産運用といった話題は、すべて日常生活の一部であり、避けては通れません。人生設計(ライフプラン)について専門家に相談することもできますが、最終的にどう生きたいか、何にお金を使いたいかを決めるのは自分自身です。だからこそ、お金の基本を自分で理解しておくことが大切です。
また、金融詐欺などのトラブルに巻き込まれないためにも、正しいお金の知識を持つことは大切です。SNSで広まる儲け話や、「○○すれば必ず儲かる」といった根拠のない投資情報に惑わされないために、基本的な金融リテラシー(お金に関する知識や判断力)を身につけておきましょう。
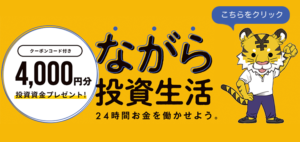
初心者がまず学ぶべき「3つの基本知識」

これからお金の勉強を始める方は、まず次の3つのテーマを順番に学んでいくことで、基礎知識をしっかり身につけることができます。
基礎知識1:収入と支出の管理
お金の勉強を始めるにあたって、最初に取り組むべきは「お金の見える化」です。多くの方が「なんとなく使っている」状態に陥りがちですが、それを脱するには記録することが第一歩となります。
毎月、自分やご家庭で「何に」「いくら」使っているかを把握するだけで、無駄な支出に気づきやすくなります。たとえば、コンビニでの買い物やサブスクの利用料など、少額の出費が積もり積もって大きな浪費につながっているケースは少なくありません。
収入に対する理想的な支出割合の例としては、以下のようなバランスが参考になります。
- 支出割合の目安
| 支出の種類 | 支出の例 | 理想的な割合 |
| 生活費 (必要なお金) |
居住費・食費・水道光熱費、通信費、日用品費、医療費、教育費、保険料、自動車維持費など | 50% |
| 予備費 (欲しいもの) |
交際費、趣味・娯楽費、被服・美容費、レジャー費など | 30% |
| 貯蓄・投資 | ― | 20% |
上記の割合は、家計管理においてよく用いられる「50:30:20の法則」と言います。この目安を参考に支出のバランスを見直すと、ムダな支出を見直しやすいでしょう。家計簿アプリを使えば、スマートフォンから手軽に記録や分析ができるため、初めて収支を管理する人にもおすすめです。
ただし、これはあくまで目安であり、理想的な支出割合は、家族構成や収入、ライフステージ、価値観によって異なります。特に子育て世帯は教育費などの負担が大きくなるため、「60:20:20」という割合を推奨する専門家も少なくありません。自分の状況に合わせて無理のない範囲で調整しましょう。
また、「先取り貯蓄」を習慣化することもおすすめです。収入が入ったら、まず一定額を貯蓄用に回し、残りのお金で生活をやりくりする方法です。このルールを守るだけで、自然と「貯められる体質」が身についていきます。
基礎知識2:ライフプランと人生に必要なお金
人生には、大きなお金が必要になるタイミングがいくつかあります。その代表が「住宅資金」「教育資金」「老後資金」という“人生の三大支出”です。
たとえば住宅を購入する場合、ローンの頭金や契約にかかる諸費用、月々のローン返済、固定資産税などがかかります。子どもの成長に合わせて必要となる教育費は、家庭の大きなライフイベントのひとつです。特に大学まで進学する場合、総額で1000万円以上かかることも少なくありません。将来の選択肢を広げるための大切なライフイベントとして、早めの準備が役立ちます。
さらに、老後資金(生活費や医療費、介護費用など)は公的年金だけで賄うのが難しい場合が多く、老後資金の目安として夫婦で2000万円以上が必要とも言われています。
こうした将来必要になるお金を「見える化」しておくことで、「いつまでに、どのくらい」準備すればよいかがわかり、焦りや不安を減らすことができます。
基礎知識3:貯蓄と投資の違い
次に知っておきたいのが、「貯蓄」と「投資」の違いです。どちらも「将来のためにお金を準備する手段」ですが、その特徴や目的には大きな違いがあります。
貯蓄の代表的な商品には「普通預金」や「定期預金」などがあります。これらは一般的に元本が保証されるため、安全性が高いのが特徴です。ただし、現在の低金利の状況では利息がごくわずかで、インフレが進むと実質的な資産価値が目減りする可能性もあります。
一方の「投資」は、値動きによる元本割れのリスクがある反面、資産を大きく増やせる可能性もあります。代表的な商品には「株式」「投資信託」などがあります。
投資を始めるにあたって理解しておきたいのが「リスクとリターンの関係」と「複利の効果」です。
投資において「リスク(値動きの幅)」と「リターン(利益)」は表裏一体の関係にあり、一般的にリターンが大きいものほどリスクも高くなります。つまり、資産が大きく増える可能性がある一方で、大きく減る可能性もあるということです。また複利とは、投資で得た利益を再投資することで、雪だるま式に資産が増えていく効果のことです。長く投資を続けるほど、この複利が大きな力を発揮します。
このような特徴から、貯蓄は近い将来に使う予定のあるお金や生活費の備えとして、投資は、長期的に運用したい資金(老後資金など)の運用方法として有効です。貯蓄と投資の特徴を理解したうえで、自分のライフスタイルやリスク許容度に合わせて、バランスよく使い分けましょう。
投資のリスクや複利については、こちらの記事で詳しく紹介しているのでチェックしてみてください。
【関連記事】
複利運用は利益が利益を生む運用方法。具体的な方法をチェック
投資におけるリスクとは?分散投資と長期投資を意識した投資を
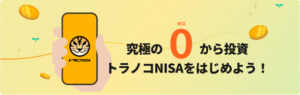
お金の勉強におすすめの方法3選
ここからは、初心者の方が始めやすいお金の勉強方法を紹介します。ご自身の始めやすい方法を見つけてチャレンジしてみましょう。
勉強方法1:マネーセミナーへの参加
お金のことを効率よく学びたい方には、専門家が講師を務める「マネーセミナー」がおすすめです。初心者向けの内容を中心に、金融商品の基礎や家計管理、資産運用の考え方などを幅広く学べるセミナーも多く開催されています。内容はセミナーによって異なるため、自分の知識レベルや目的に合っているかを事前に確認しておくと安心です。
また、セミナーではその場で疑問を質問できるので、曖昧な知識をしっかりと理解に変えることができます。最近では、オンライン形式の無料セミナーも充実しているため、忙しい社会人でも参加しやすいのが魅力です。
勉強方法2:お金に関する資格勉強
より体系的にお金の知識を学びたい方には、「ファイナンシャル・プランナー(FP)」などの資格取得に挑戦するのもおすすめです。FPの学習内容は、家計管理、保険、税金、不動産、相続など多岐にわたり、実生活で役立つ知識が満載です。
資格を取得すれば、自分自身の生活に役立つだけでなく、将来的に副業や仕事の場面で知識を活かせる可能性があります。特に金融業界では、一定の金融知識が必要になるため、こうした資格が求められることもあります。
勉強方法3:動画学習
もっと気軽に始めたい方におすすめなのが「動画学習」です。最近はYouTubeなどの無料動画でも、わかりやすくお金の仕組みを解説しているコンテンツが多数あります。目と耳で学べるため、書籍よりもスムーズに理解できるという方も多いでしょう。ご自身のペースで繰り返し学べるので、忙しい方でも時間を無理なく確保しながら学べる点が魅力です。
「トラの知恵」で展開している「学習動画シリーズ」は、お金の基礎知識をわかりやすくまとめており、初心者の方でも手軽に学べます。ぜひ一度ご覧ください。
資産運用アプリ「トラノコ」では、トラノコクイズ(Toranoko Academy)のコーナーで、「資産形成」「お金と生活」「トラノコ活用術」の3テーマについて金融リテラシーを高められます。
コツコツ投資をしつつ、楽しみながらお金の知識を身につけたい方は、ぜひ気軽に試してみてください。
さらに、お金に関する具体的な悩みや相談には、無料相談サービスの利用も大変役立ちます。住宅購入や教育資金、老後資金など具体的な内容を相談したいシーンも出てくるでしょう。動画学習と合わせて、こうした相談先も活用しながら、お金の知識をしっかり身につけていきましょう。
参考記事:お金の無料相談ができる場所は?相談先の選び方とメリット・デメリットを紹介
トラの知恵「トラの知恵の学習動画シリーズ」
トラノコ「Q.トラノコクイズとは何ですか」
まとめ
お金の知識は、一度身につければ一生の財産になります。日常のちょっとした出費を見直すだけでも、将来への備えにつながり、ライフプランや投資の知識があれば、人生の選択肢も広げやすくなるでしょう。
この秋から始めれば、年末には「お金についてわかるようになってきた」という実感が持てるはずです。まずは、動画などの無料コンテンツで気軽に学ぶことからスタートしてみてください。自分や家族の未来のために、今こそ「お金の勉強」を始めてみませんか?