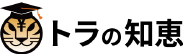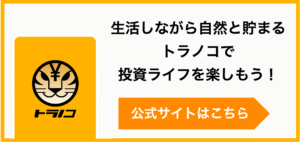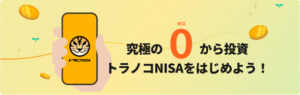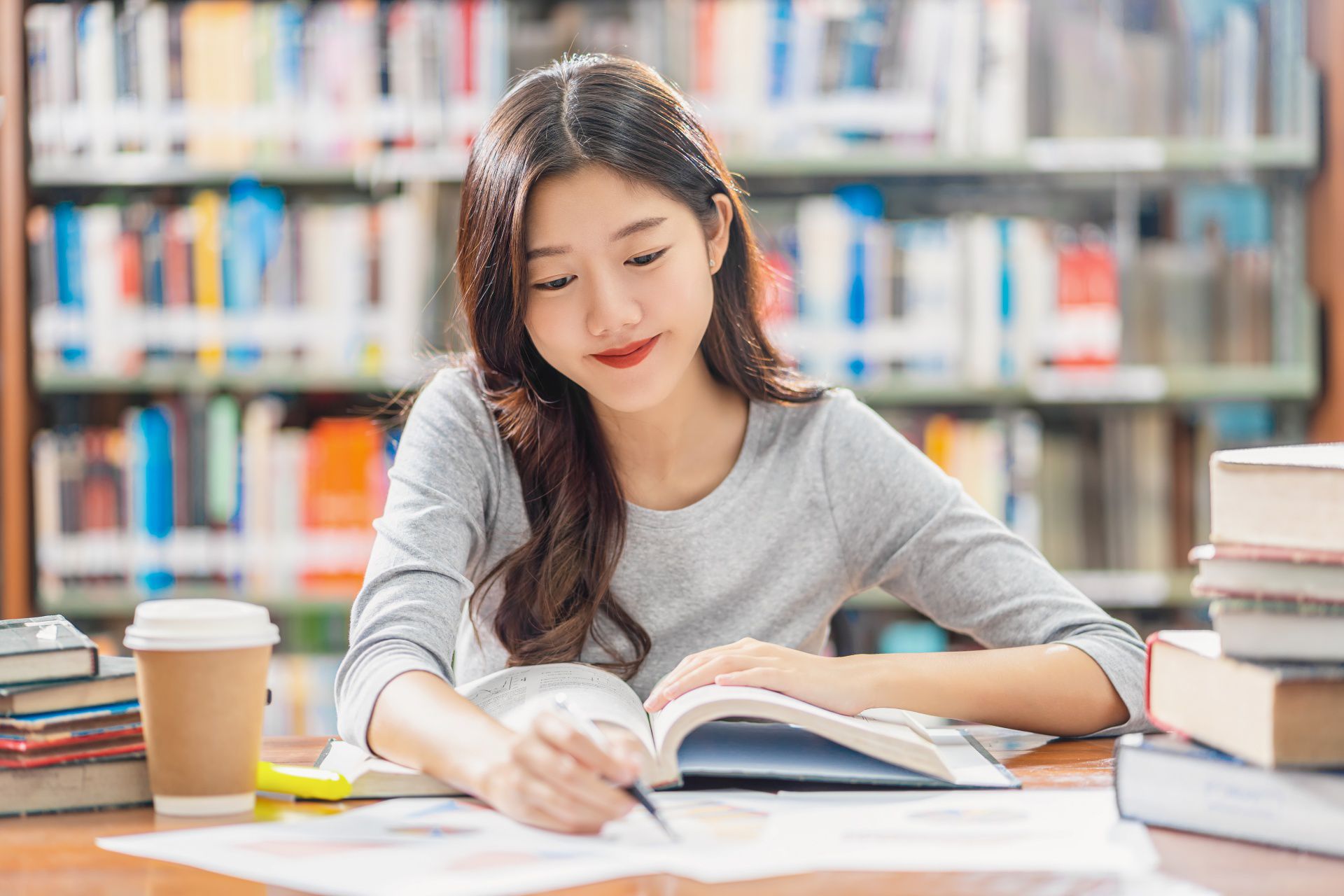物価高対策で食費を節約するコツは?無理なく支出を抑える方法・考え方を紹介
公開日:
物価高が続く中、家計を守るために食費をなるべく節約することは重要です。しかし、無理な節約はストレスが溜まり、健康を損なう可能性もあります。食費を節約するときは、どのように取り組めばよいのでしょうか。
この記事では、1ヵ月の食費の平均額や無理なく食費を抑えるコツ、注意点を紹介します。物価高対策として、食費を見直したい方はぜひ参考にしてください。
1ヵ月の食費の平均額は?

総務省の家計調査によると、1カ月の食費の平均額は以下の通りです。
| 世帯区分 | 食費の月平均額 |
| 二人以上世帯 | 8万9,936円 |
| 単身世帯 | 4万8,204円 |
| 総世帯 | 7万4,187円 |
出典)総務省統計局「家計調査報告〔家計収支編〕2024年(令和6年)平均結果の概要」
同調査によると、二人以上世帯のエンゲル係数は28.3%となっています。エンゲル係数とは、消費支出に占める食費の割合です。
なお、食費と消費支出の月平均額から単純計算すると、単身世帯のエンゲル係数(概算)は28.4%(食費4万8,204円÷消費支出16万9,547円×100)となります。
食費はいくらに抑えるのが理想?
理想的な食費の目安は、収入や世帯人数によって異なります。食費を見直す際は、エンゲル係数を目安にするのが有効です。
先ほど紹介した総務省の家計調査によれば、2024年のエンゲル係数は二人以上世帯・単身世帯のどちらも約28%です。仮に毎月の生活費が25万円であれば、食費の目安は7万円(25万円×28%)となります。
まずはエンゲル係数が平均値以下になることを目指しましょう。
食品の値上げが起きる要因

食品の値上げが起きる要因として、主に以下の7つが考えられます。
- 原材料価格の高騰
- 物流費の上昇
- 人件費の上昇
- 円安の進行
- 天候不順
- 食料自給率の低さ
多くの場合、複数の要因が重なって食品の値上げが発生します。ここでは、それぞれの要因について詳しくみていきましょう。
原材料価格の高騰
農作物や畜産物の生産量が低下したり、生産コストが上がったりすると原材料価格が高騰し、食品の値上げにつながります。例えば、小麦価格の上昇はパンや麺類、飼料価格の上昇は肉や卵などの価格に反映されやすくなります。
物流費の上昇
燃料費の高騰やドライバー不足の影響による物流費の上昇も、食品の値上げ要因の一つです。食品を輸送するコストが増加するため、販売価格に転嫁されることがあります。
人件費の上昇
人手不足の中で人材を確保するための手段として、賃金の引き上げが行われることがあります。人件費の上昇は食品の製造・販売コストを増加させるため、食品の値上げにつながります。
円安の進行
円安が進行すると、輸入品の価格が高くなります。仮に100ドルの商品を輸入する場合、1ドル=100円なら支払額は1万円(100ドル×100円)です。しかし、円安が進行して1ドル=150円になると、支払額は1万5,000円(100ドル×150円)に増加します。
日本は多くの食品を輸入に頼っていることに加えて、石油や天然ガスなどのエネルギーも海外依存度が高い状況です。円安の進行は原材料価格や物流費の上昇要因にもなるため、結果として食品の値上げが起きやすくなります。
天候不順
自然災害や異常気象などの天候不順は、農作物の不作や漁獲量の減少などを引き起こし、食品の供給不足を招きます。供給量が減少することで、食品価格が高騰することがあります。
食料自給率の低さ
食料自給率とは、国内で供給される食料のうち、国内で生産された食料が占める割合のことです。2023年度の日本の食料自給率は熱量で換算するカロリーベースが38%、金額で換算する生産量ベースが61%となっており、いずれも長期では減少傾向が続いています。
食料自給率が低いと、海外の食料価格の変動や輸入量、円安の影響を受けやすくなるため、食品の値上げを招くことがあります。
物価高対策!無理なく食費を節約するコツ

食品の値上げが続く中、家計への影響を最小限に抑えるには、生活スタイルに合わせた工夫が必要です。ここでは、無理なく食費を節約するコツを7つ紹介します。
1ヵ月の食費の予算を決める
まずは、1ヵ月の食費の予算を決めましょう。予算を決めることで無駄遣いを防ぎ、計画的に食費を管理できます。予算は収入や家族構成などを考慮して、無理のない範囲で設定することが大切です。
予算を決める際は、自炊と外食を分けるのがおすすめです。それぞれの予算を決めることで、より細かく支出を管理できます。
外食を減らして自炊を心掛ける
外食は費用がかさむため、できるだけ自炊を心掛けましょう。自炊することで、食材を無駄なく使い切ることができ、栄養バランスも調整しやすくなります。
お弁当を持参することも、外食費の節約に効果的です。お弁当を作る際は、夕食のおかずを多めに作って詰めたり、冷凍食品を活用したりすると手間を省けるでしょう。
比較的安い食材を積極的に活用する
食費を節約するために、比較的安い食材を積極的に活用しましょう。例えば、鶏むね肉や豚こま肉、もやし、きのこ類などは比較的安価で栄養価も豊富です。これらの食材を上手に活用することで、食費を抑えながらも満足感のあるメニューを作ることができるでしょう。
また、旬の食材を取り入れることもおすすめです。旬の食材は安く手に入りやすく、栄養価も高い傾向にあります。
まとめ買いをする
特売日などにまとめ買いをすれば、割安な価格で購入できます。買い物の回数が減り、無駄遣いを防ぐ効果が期待できるのもメリットです。
ただし、食材を使い切れるかを考えて購入量を調節する必要があります。特に生鮮食品は傷みやすいため、計画的に使い切れる量を買いましょう。冷凍保存を活用するのもおすすめです。
作り置きをする
時間のあるときに作り置きをしておけば、毎日の調理時間を短縮し、食材の無駄を減らすことができます。お弁当のおかずにも活用できるため、食費の節約にも効果的です。
作り置きをする際は、日持ちする食材やメニューを選ぶことがポイントです。衛生面に注意して、冷蔵庫や冷凍庫で適切に保存しましょう。
コンビニや自動販売機の利用を控える
コンビニや自動販売機はスーパーに比べて割高な商品が多いため、利用を控えることで食費を節約できます。可能であれば、飲み物はお茶や水を持参するといいでしょう。
仕事帰りなどにコンビニへ立ち寄る習慣があると、不要なお菓子などを買ってしまう可能性が高まるので注意が必要です。
お菓子やお酒の量を減らす
お菓子やお酒は嗜好品であり、買いすぎると食費を圧迫する要因になります。完全になくす必要はありませんが、量を減らすことで食費を節約することができ、健康面にもよい影響を与えるでしょう。
食費を節約する際の注意点

食費の節約は大切ですが、無理をすると長続きしません。家計への負担を減らすためにも、次の点に注意しましょう。
外食や嗜好品を我慢しすぎない
食費を節約するために、外食や嗜好品を完全に我慢する必要はありません。我慢しすぎるとストレスが溜まり、節約が長続きしなくなる可能性があります。「外食は月に〇回まで」「お菓子は週末だけ」など、自分なりのルールを決めて無理のない範囲で取り組みましょう。
健康を損なうような節約は避ける
食費を抑えるうえで最も注意すべきことは、健康を損なうような節約を避けることです。例えば、食事の量や回数を極端に減らしたり、インスタント食品ばかりを食べたりすることは、十分な栄養を摂ることができず体調不良の原因になります。
食費を節約する場合でも栄養価の高い食材を選び、自炊を中心にバランスの取れた食事を心掛けることが大切です。
まとめ
家計管理において食費の節約は重要ですが、無理をするとストレスが溜まり、心身の健康を損なう可能性があります。今回紹介した方法を参考に、できる範囲で無理なく、楽しみながら食費の節約に取り組みましょう。
また、食費の節約効果は家計全体からみると限定的です。食費だけでなく、固定費を中心に光熱費や被服費、交際費など家計全体を見直すことが大切です。